難解な現代思想を語る哲学者と、高度な数式を駆使し先端テクノロジーに挑む工学研究者は一見すると対極の存在にみえる。だが人工知能(AI)が人間の頭脳を凌駕する可能性がささやかれたり、人間とコミュニケーションできるロボットが生活の中に入ってくることが現実となる時代に、両者は「人間とは何か」という問いを共有するようになった。それは本来無機物であるロボットが鏡となって人間を照らし、その本質を知る手がかりになると考えるからだ。大阪大学大学院人間科学研究科の檜垣立哉教授(フランス現代思想)もその一人だ。「人間とは何か、生命とは何か、ロボットとは何か」について哲学者の立場から語ってもらった。
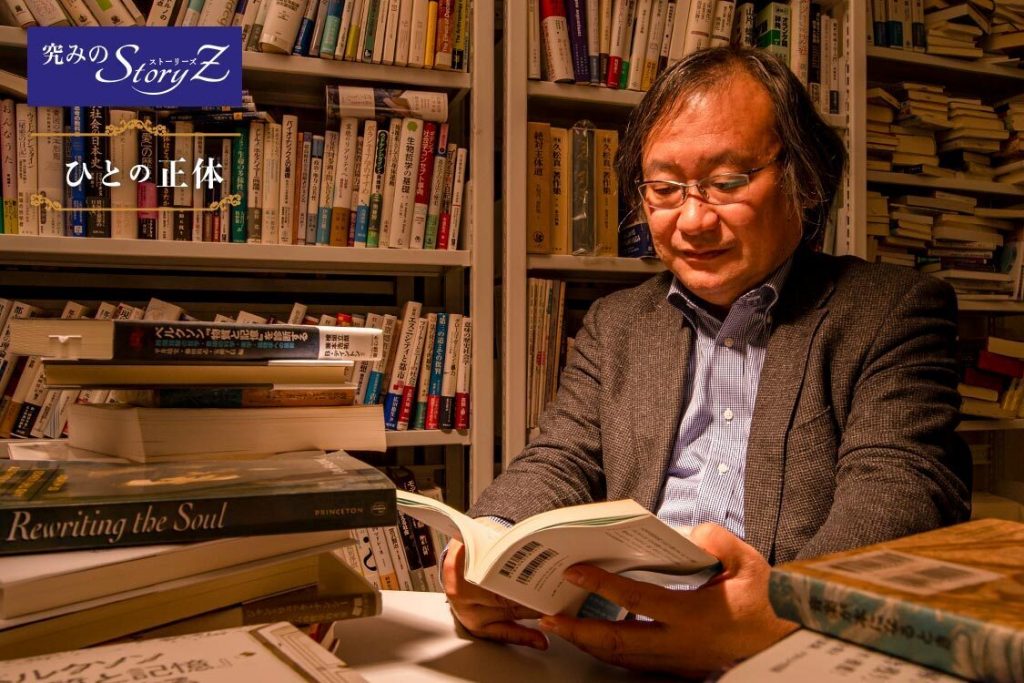
哲学者がロボットを研究する理由
檜垣教授はジル・ドゥルーズ(1925~1995)などのフランス現代思想のほか、西田幾多郎(1870~1945)を中心とした京都学派など日本哲学も幅広く研究。その一方で、最先端のロボット技術にも哲学者として目を注いでいる。
「生きること、その裏返しとして死ぬことを考える<生命の哲学>が私のテーマです。技術が変われば人間の価値観も変わる。さらに何が生命なのか、何が生きているということなのか、その定義も変わる。認知発達ロボティクスの浅田稔先生(現・大阪大学特任教授)にインタビューしたとき、究極的にはロボットが<生きている>という状態をどう考えたらよいかという話になりました。人間と見分けがつかないロボット製作が可能になれば、生物学的なそれとは違った<生>の定義にならざるをえない。じゃあ哲学は何を考えるべきなのか。人間の似姿としてのロボットを通して、<人間が生きるとは>とか、<人間が死ぬとは>を反証的に考える必要があると思ったのです」
20世紀後半に急速に発達した生命科学は哲学にとっても重要なテーマだった。とくに体外受精やクローン、臓器移植と脳死の問題など、従来の生命観・死生観を揺るがす技術は、私たちにさまざまな問いを突き付け、難しい決断を求めた。こうした問題について社会的合意を探るのが哲学の一分野である生命倫理の役割だが、檜垣教授は「生命や倫理をめぐる議論が、臓器移植など医学上の必要性に引きずられてしまった。もちろん社会的合意や常識は必要だが、哲学はそれだけじゃないぞ、哲学は生きること、死ぬことを根本から考えねばならないんだ」と強く思ったという。
「生命倫理は1980~90年代に制度化され、今では大学の医学部が担当している。それはそれで大切なんですが、倫理はある種の価値観を前提とした線引きの問題です。しかし、太古の昔から技術が変われば人間も変わる。ピストルができれば戦争の仕方が変わるし、グーテンベルクの活版印刷ができれば人間と知のありかたが変わる。紙の本が電子データに置き換われば、学問の仕方だって変わる。昔は哲学教師がハイデガーの『存在と時間』を講義するとき、『182ページの上から何行目になんとかという単語があり、その言葉はこの本のなかに計5カ所でてくる』なんてやってたわけです。それが今はパソコンで検索すればできてしまう。人間が記憶でやってきたことがすべて置き換わります」
技術の変化が、人間の知のあり方そのものをゆさぶっている。

競馬を通して人間を考える
こうした状況は、人工知能やロボットの驚異的な発達で第3次ロボットブームといわれる昨今、新しい形をとって立ち現れる。大阪大学でも、「バイオサイエンスの時代における人間の未来」を探る学際プロジェクトが2010年代に設けられ、檜垣教授が研究代表者を務めた。同じような問題意識は、工学系、人文系の枠を超えて海外でも共有され、2012年にはドイツのビーレフェルト大学で「ロボット人類学」に関するワークショップが開催された。
ワークショップに参加し、「生命とロボット/人間とロボット」のテーマで発表した檜垣教授は「ロボット研究者の議論を聞いていると、完全に哲学なんですね。なにをもってロボットが意志的に動いているといえるのか、とか。その問いかけ自身が人間に返ってくる。ぼくだって、自分の手が本当に自分の意志で動いているかなんて分からないんですから」と苦笑する。
そして、アメリカの生理学者ベンジャミン・リベットによる有名な実験の例を挙げた。それによると、人間が自分の手を動かそうと意識するゼロ・コンマ何秒か前に、既に脳波が活発化するというのだ。自由意思を持つことが人間をロボットと区別するという考えがある。だが実験結果は「われわれが手を動かそうと意識をした、その直前に脳波(準備電位)が現れたとすれば、それは自由な意思と言えるのだろうか」という疑問を投げかけている。
檜垣教授にとって、人間という存在は「生まれる、生殖する、老いる、死ぬ」ということに尽きるという。いくら高度な知能を持つからといって動物としての制約から外れることはできない。一方で、やはり動物からはみ出してしまう側面があるからややこしい。その最たるものは言語かもしれない。だがそれは人間が進化の必然として獲得したものなのか、それとも偶然の産物なのか。
「生命の哲学にとって偶発性や偶然性をどう考えるかは難しいんです。現代はエビデンスと再現性のない事象を科学とは呼ばない。だから進化論が科学かというと、難しい問題なのです。アフリカのあるところで、とあるサルが立ち上がったら、なんか頭が大きくなっちゃって……。それはものすごい特定条件のもとで起きた、一回きりのできごとです。言語の獲得も、そうです。そもそも言葉なんて化石に残らないし、考古学的にもたどれない。進化に再現性なんてまったくない」
しかし、そうしたサルの後裔が言語を獲得し、高度な文明を築いて世界の支配者として君臨している。たかだか偶然性と偶発性の産物でしかなかったはずなのに。
「サルでもチーターでも動物は言葉なしに生きています。人間は言葉を使わなければ、もはや他人とコミュニケーションも取れないし、社会性も形成できない。これってなんなんだろう? 人間という生きものを考えたとき、ある種の柔軟性というか、無駄というか、奇妙なというか、あまり合理的ではない動きをします」
その一つが、「賭け」という行為だ。
大の競馬ファンとして知られる檜垣教授は「競馬をやっていると分かるんですが、どうしたら当たるかを一生懸命考えて馬券を買うんですね。しかし、走っているのは自然物です。どんな強い馬でも脚を折ったら終わりだし、隣の馬とぶつかったりする。始まってみなければレースは分からない。しかも、面白いことに馬券が当たるとみんな『おっ!』と驚く。外れたときは驚かないんです。当てるために馬券を買っているのに矛盾ですよね」
ままならない事象に賭けてみる行為を、「偶然性を遊ぶというか、人間が持っている絶対的な特性」とみている。そもそも、私たちが生を受けたことも偶然。生活の中でも、私たちは偶然性を知らず知らず受け入れながら生きている。
逆らえない自然に逆らう

偶然性を遊ぶ人間は予測できない事態に陥っても、なんとか対処しようとする。しかし、ロボットや人工知能(AI)には「与えられた枠組みの中でしか、課題に対処できない」(フレーム問題)という壁がある。
「たとえば人間が電車に乗るときにおこなっている判断って、膨大なものがあります。だからロボットを一人で電車に乗せるというのは大変なんです。電車が遅れたり、運休しても、人間なら臨機応変に判断します。ロボットはあらかじめ指示がなければ判断できない。電車が火事になったら人間は逃げますが、ロボットは『火事が起きました。私はどうすればいいんでしょうか?』と停止してしまう。不確実性を受容し、<賭け>をする人間との違いがここにあります」
あいまいで、矛盾に満ち、ときに合理性に欠けた行動に突き進む。こうした人間の困った特性は、いざ計算不能の事態に出会ったとき、ある種の強みに転化するのかもしれない。大切なお金を競馬に注ぎ込むことも、「人生の修練」につながっている。とも言える。
さて「賭け」を楽しみながら、ロボット研究のゆくえを見つめる哲学者に「人間の正体は?」という質問をぶつけてみた。
「経済人類学者の栗本慎一郎さんが『パンツをはいたサル』と表現していましたが、人間って知能を持ち、真理や美や崇高さを追求して、自分を偉い存在だと信じています。一方で必ず死ぬ存在であり、完全に動物でしかありません。それなのにテクノロジーを駆使して偶然性をつぶし、合理的に未来を予測しようとして変な方向に突っ走ってしまう。未来予測なんてほとんど当たりません。自然には逆らえないのに、それに逆らおうとして自己撞着に陥っている存在が人間ですね」
- 檜垣教授にとって研究とは
- ぼくにとって研究とは「生きている」ことそのものじゃないでしょうか。 哲学ってなんでも研究対象になります。食べることや老いること、音楽でも、競馬でも、新型コロナでも。自分が生きていることのなかで立ち現れる事象について考えること。目下の研究テーマは「住むこと」です。
檜垣 立哉(ひがき たつや)
大阪大学大学院人間科学研究科 教授

「ひと」とは何か? 古来から人々が問うてきた大きなテーマ。 生命は未だ神秘のベールに包まれ、今なおあらゆる角度から挑み続ける研究者たち。
2022年のいま、「ひと」はどこまで明らかになったのか? アンドロイド研究の第一人者石黒浩教授(基礎工学研究科)らが語る 人の正体に迫る挑戦の物語。
<<<マイハンダイアプリにて順次公開予定!>>>
アンドロイドに「わたし」をみる 技術がひとを多様にし、不幸をひとつひとつ消し去っていく 基礎工学研究科 石黒浩栄誉教授
あなたはなぜ“やわらかい”のか。 知能と身体の深い関係 基礎工学研究科 細田耕教授
幼なじみがロボットになる日 心分かち合う“相棒”となるために 基礎工学研究科 長井隆行教授
脳がつくりだす“あなたの世界” 「時間」と「ここ」と「わたし」の真実 生命機能研究科 北澤茂教授
私の心はどこに存在するのか 瞬きから覗き見る脳内の風景 生命機能研究科 中野珠実准教授
アバターの責任誰が負う?法律で描く社会のかたち 社会技術共創研究センター 赤坂亮太准教授
ロボットと歩み 人間を解く 先導的学際研究機構 浅田稔特任教授
人間は偶然を楽しむ 人間科学研究科 檜垣立哉教授


