
「まちかね祭、開催決定!」と、19日後の「まちかね祭延期のお知らせ」。阪大生にとって、この秋の2大ニュースだったことと思います。まちかね祭を運営する「大阪大学大学祭中央実行委員会」(以後、中実 )の委員長、大谷真寛さんは、「今できる最大限のことをやります。期待はしないでほしいけど、待っていてください」と、悔しい表情を浮かべながらも前向きに語ってくれました。まちかね祭3日間のために彼が奔走した期間は8ヵ月。初めての「対面×オンライン開催」に向け、どんな想いで、どんな準備を重ねてきたのか。そして今年のまちかね祭はどうなるのか。大谷さんに、これまでの道のりと、いま現在の等身大の想いを取材しました。
○まちかね祭Webサイト
https://machikanesai.com/
○まちかね祭の延期について(2020.11.11)
https://twitter.com/machikanesai/status/1326362382830985216
https://machikanesai.com/
○まちかね祭の延期について(2020.11.11)
https://twitter.com/machikanesai/status/1326362382830985216
プロフィール
大谷 真寛(おおたに まひろ)
大阪大学 人間科学部3年生。「いちょう祭」「まちかね祭」をはじめとする学生企画イベントの運営を行う「大阪大学大学祭中央実行委員会」の委員長を務める。
中実の委員長でありながら、漕艇部のマネージャーでもある。学部では人権やジェンダーに関する研究を行う。そのきっかけとなったのは、中学生時代に腐女子から借りたBL漫画だそう。
※編集部より※ 記事は2020年12月2日取材当時の内容に基づき執筆したものです。記事公開時には、まちかね祭に関する状況が異なっている可能性があります。
- 日本でほぼ唯一。Withコロナで大学祭を開催した、事例になるはずだった。
- 2020年3月18日。忘れもしないあの日から、まちかね祭実現を目指していた。
- 実現に向けた仕掛けその1:Webサーオリ
- 実現に向けた仕掛けその2:サークル合同説明会
- 実現に向けた仕掛けその3:コロナ対応のシステム開発
- 学生団体ファースト。関係する人々の声に耳を傾け、大学祭を皆でつくっていく。
- 「オンライン✕対面」という、新しい時代の大学祭。
- 気にしない。一人で背負わない。仲間に頼る。
- 大学祭や課外活動は、新しい視点を見つけるきっかけになる。
- 開催はどうなる?中実の動きと、まちかね祭のこれから。
- 番外編:まちかね祭が予定通り開催されていたら。本当は声を大にして、大谷さんが皆さんに伝えたかったメッセージ。
日本でほぼ唯一。Withコロナで大学祭を開催した、事例になるはずだった。
— まさか2回も、大谷さんに取材させていただくとは思ってもいませんでした。前回は10月末だったので、まちかね祭に向けてラストスパートをかけている時でしたね。
2週間で、こんなにも状況が変わるとは。実は、阪大と同じくらいの規模の総合大学で学祭を開催するのは、日本中で法政大学さんと阪大くらいだったんです。つまり、阪大が失敗すると、全国の大学に影響を与えてしまうことになる。逆に、阪大が成功すると、コロナ禍で開催したひとつの事例になるので、全国の大学祭の背中を押すことができる。そういった意味で、開催にあたってプレッシャーを感じていました。まあでも、ネガティブなことはあまり考えないタイプなので。新しい様式の大学祭を確立し、「大阪大学まちかね祭」の名を全国に轟かせてやろうという意気込みでいたんです。
— 本来なら今頃、まちかね祭を無事に終えて大谷さんは引退するはずだったのでは…。
そうですね。11月に入ってから、新型コロナ感染者数が大阪府内で急激に増えて、雲行きが怪しいなと感じていました。もしこのまま感染が拡大した場合、開催すべきなのか、規模を縮小したり形を変えたり対策を講じたほうが良いのか、うっすら考え始めていたんです。
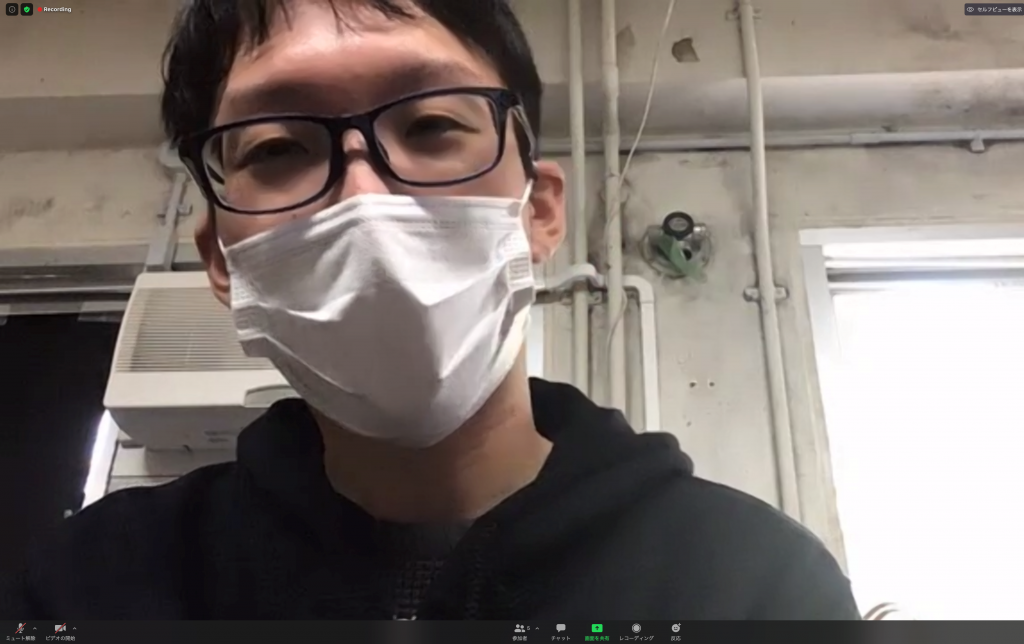
— 今回は、大学側(学生・キャリア支援課)から「延期の勧告」を受けたそうですね。
本当は、「延期の決定」が言い渡される予定だったんです。バイトの休憩中に中実委員から「延期になるかもしれない」と連絡がきて、すぐさま大学当局に連絡をとりました。「まちかね祭は、学生が主体となって行うイベント。これまでにも学生団体をはじめ各所と連携をとり、Withコロナ時代の大学祭を模索しながら準備を積み重ねてきた。大学が一方的に判断を下すのではなく、勧告という形にしてほしい」とお願いしたんです。それを大学側は快く受け入れてくださって。勧告の通知を受け取ってから、中実の判断としてまちかね祭延期を決定しました。
2020年3月18日。忘れもしないあの日から、まちかね祭実現を目指していた。
— 大学に言われるがままではなく、自分たちで判断する姿勢を貫いているんですね。そこまでして、学生主導にこだわる理由って何でしょうか?
3月18日。忘れもしないあの日からですね。
— 3月18日…何があったんですか?
大学から「いちょう祭」中止の知らせがあった日です。いちょう祭は毎年5月に開催される春の学祭。今年はコロナの影響で中止になったのですが、我々が運営を一部担っているにも関わらず、事前に相談や共有が何もないまま中止の知らせがきて。
— 大学の一方的な判断だったんですね。
僕が運転免許を取った時のことで、今でもしっかりと覚えていますよ(笑)。門真の免許センターで写真撮るのを待っていた時に、中実のメンバーから電話がかかってきたんです。「いちょう祭、中止らしいけど知ってる?」って。委員長である僕ですら知らない情報で、すぐさま大学の担当職員に「どうなってるんですか?」って電話をかけました。大学側としては迅速な判断が必要だったと思うんですが、我々は学祭に出店したりイベントを企画したりする学生団体と連絡調整をしている立場なので、事前に一報欲しかったですね。

その日のうちに中実の幹部全員が集まり、話し合いの結果、大学当局に抗議声明を出すことが決まりました。
— 今年は、イレギュラーなことばかりでしたもんね。大学側としても難しい判断だったと思います。とは言え、抗議声明を出す理由が、中実にはあったわけですよね。
はい。僕は普段、人権に関連する研究をしているということもあって、然るべき手順で情報通達がなされていないと思われる状況に怒りが沸いてきたんです。それに、大阪大学憲章には「対話の促進:大阪大学は、あらゆる意味での対話を重んじ、教職員および学生は、それぞれの立場から、また、その立場を超えて、互いに相手を尊重する」と書かれてあります。でも現実は、対話がなかった。ここで一度委員長として、きちんと声を挙げなければならないと思ったんです。
— 研究者の卵としての怒り、委員長としての怒り。その感情があったとしても、抗議声明を発表するのに、踏みとどまる気持ちはありませんでしたか?
ありましたね。叩かれるだろうな、とは思っていました。それに発表当時は、大学本部が揺れたって聞いてます(笑)。でもそれがきっかけで、以前にも増して大学側と対話するようになり、今回のように「延期勧告」を依頼できるほど良好な関係を築くことができました。
— 大学祭のために、そこまでするんですね。
「いちょう祭」は中止。あの忘れもしない3月18日から、我々はまちかね祭の実現めがけて動き始めました。いかに大学を説得し、いかに完璧に実行するか。「やったんで!目に物見せてやる!」っていう気持ちでしたね。

実現に向けた仕掛けその1:Webサーオリ
— まちかね祭実現に向けてどんな準備を積み重ねてこられたんですか?
まずは、人が密集しやすいリアルな場での開催が難しくても、オンラインイベントならできないかと考えました。それが形になったのが、4月に開催した「Webサーオリ」です。これまで対面で行っていた新歓イベントを、オンラインで開催しました。入学したての1年生にとって、大学生になったのに大学に来れない、友人もつくれない、サークルも入れないという状況をどうにかしたい。そんな想いから生まれたイベントでもあります。
— どんなことをされたんですか?
ツイキャスやZoom、YouTubeなどの動画配信サービスを用いて、団体の活動を配信しました。実施に向けて、各団体から情報を共有してもらうためのフォームを作成し、配信内容を取りまとめたり、視聴できる環境をつくったりと、1ヵ月で準備しました。
— 早っ!初の試みですよね?これまでリアルな場で開催していたイベントを、オンラインに移行するって、簡単なことではないと思うのですが…。
それが中実にはですね、優秀なメンバーが集まっていまして。「広報局Web」という部署のメンバーがWebサーオリを実現するためのシステムを全て開発してくれました。
もともと、今年度の学祭に向けて彼らは「大学祭運営システム」をつくってくれていました。これまで各団体とは書面でやりとりをしていたのですが、面倒なので全部フォーム化して。団体情報が一覧で確認できたり、どんなやりとりをしたのかが分かったりと、カルテのようなシステムです。

実現に向けた仕掛けその2:サークル合同説明会
オンラインイベントが実現できたので、次はどうすれば対面でイベント開催できるのかを考え始めました。そんな時、「新入生の必修科目を学内で行うので、そのタイミングでサークル説明会をしてみたらどうか?」と、大学側から提案があったんです。
— ちょうど良いタイミングですね。
「いちょう祭」が中止になった後、まちかね祭のアイデアや企画案を小出しで提案していたので、我々にやる気があることを知ってもらっていて、声がかかったんだと思います。大学の提案を受けて、大阪大学安全衛生管理部の山本先生、そして担当職員の方と議論を重ねながら、コロナ禍でもより安全で安心できる対面イベントのあり方を検討しました。
実現に向けた仕掛けその3:コロナ対応のシステム開発
具体的には中実の新しい部署「コロナ対策本部」を立ち上げて、コロナ対策のガイドラインの作成と、「入場管理システム」を開発・導入しました。
— またもやシステム!
はい。参加者が入場する際にQRコードを発行することで、何時に通過したのかが分かるというものです。こうした環境を整えたことで、なんとか対面で「サークル合同説明会」を開催することができました。
— やってみていかがでしたか?
1年生だけでなく、学生団体からの嬉しい声を多くいただきました。「コロナなのに対面イベントやってくれるの!?中実ありがとう!」みたいな感じで。やっぱり、オンラインよりも対面の方が盛り上がるんですよね。
— コロナの影響で、対面イベントの開催が困難になっていますもんね。そんな中、可能性を模索し、学生団体さんの想いを形にされたことが評価につながったのでしょうか。
これまでの中実はどちらかというと学生団体を取り締まる場面のほうが多く、「中実は自分たちのやりたいことをやらせてくれない」と、あまり良く思われない方もいたと思います。今もやむを得ない事情で、制限を設けてしまうことがあるのですが、なるべく団体さんのやりたいことを実現できるようにしたい。その想いが伝わったのなら、嬉しく思います。それに、団体の皆さんに喜んでもらえるのは、中実のメンバーにとっても本当に嬉しいんですよ。感謝されるって、やる気上がりますよね。

学生団体ファースト。関係する人々の声に耳を傾け、大学祭を皆でつくっていく。
— お話を伺っていると、中実の皆さんがやりたいことをやるというよりも、学生団体の皆さんを尊重する姿勢が感じられます。
中実が一方的にルールを決めて、学生団体の活動に制限をかけていたのが従来の形。でも、「いちょう祭」中止の件で、僕たち自身も対話の重要性を再認識したんです。特に、今年はコロナで例年どおりのイベントができないし、感染症対策など守ってもらわなければならないこともある。こうした状況だからこそ、まちかね祭の実現に向けて、学生団体の皆さんのご協力とご理解が必要でした。そうした背景もあって、学生団体の声を聞く機会を例年よりも多く設けたんです。コロナ対策を推進するための事前説明会や、企画相談会など、日々のメッセージのやりとりだけでなく、声を聞くための場を開きました。

その中で、我々にはない視点からのご意見をいただいたりもして、より安全で安心して楽しめるまちかね祭の実現に向けて、方針を固めることができました。
—「いちょう祭」中止での経験もあるかと思いますが、対話や声を聞くことを大切にされた理由って何ですか?
僕がやってるアルバイトは、ビジネスホテルのフロントなんです。そこではお客様の表情や目線、手荷物を見て、一人ひとりに合わせた接客をするように心がけています。その経験が大きいかもしれません。まずは、相手を見る。相手の話を聞く。接客の基本ですよね。中実の活動にも応用できるなと思い、一方的なコミュニケーションではなく対話を軸とした運営を心がけるようになりました。

「オンライン✕対面」という、新しい時代の大学祭。
— これまでにお伺いしたたくさんの活動があって、今に至るわけですね。
大学からまちかね祭開催の決定通知を受け取ったのが、10月23日の金曜日。11月20日(金)〜22日(日)に開催する予定だったので、その時点でもう1ヵ月をきっていたんですよね。「決定が遅い!」とも思いつつ、「ようやく正式なGOサインが出たか!」と、準備に燃えていました。結果的に延期になってしまいましたが、中実の努力だけではなく、学生団体の皆さんが協力してくれたことが、開催決定の後押しになったと思います。
— 今回は、オンライン&対面での開催予定だったかと思います。そのスタイルにされたのはどういった理由ですか?
オンライン&対面でやりたいと言い始めたのは僕なんですよ。このスタイルにしたのは、より多くの方に大学祭を楽しんでいただきたいという想いからです。毎年、まちかね祭には多くの地域住民の方にも来場いただいており、地域の方のおかげでやってこれていると言っても過言ではありません。ですが大学側から、不特定多数の参加者が学内に集うのは気がかりだと意見があり、特定多数にするために参加者を限定することになりました。ここで開発した「入場管理システム」が本領発揮するはずだったんですけどね。

気にしない。一人で背負わない。仲間に頼る。
— これまでの長い道のりを、中実の皆さんと一緒にどうやって乗り越えてこられたのでしょうか。さらに大谷さんは漕艇部のマネージャーでリーダー格の主務でもあると伺いました。委員長と合わせて膨大な業務量だと思うのですが、大谷さんからはあまり大変さが伝わってこないんですよね。ひょひょうとしているというか。

気にしないのが一番です。というより、僕が気にしないようにサポートしてくれる人たちが周りにいるんです。僕はリマインドが苦手で、副委員長にリマインドをお願いしているんですが「これちゃんとやった?」って言ってくれるし。僕が気にしなさすぎて、たまに怒られるんですけどね。

僕だけがマネジメントしているわけではなくて、中実全員でマネジメントする姿勢があり、僕も安心して任せることができています。
— メンバーとの関係性づくりや、チームづくりで心がけていることはありますか?
仕事だと大まかな方針は伝えますが、ほとんど任せるんですよ。細かく指示を出さない。例えば、入場管理システムは「ユニバのハリーポッターみたいな感じにしてくれへん?」って開発チームに投げたくらいなんです。だから僕、歴代で一番放任主義って言われているらしいですよ。
— それで仕事が成り立つって、良いチームワークだなと思います。
中実は皆、官僚みたいにまじめなんです。僕が一番不まじめで、何もしてないと思ってる人もいると思いますよ。ただ部室で漫画読んでる人、みたいな(笑)。

右:中実のコロナ対策副本部長を務める工学部応用自然科学科3年生の坂部さん。
— メンバーのお二人に質問です。大谷さんと一緒に活動されていて、良いなと思うことって何ですか?普段は言えないけど、ここだから言えるぶっちゃけ話もあればぜひ!
坂部さん:大谷さんは、仕事をするうえで走る能力が高いですね。中実は口下手な人が多いんですけど、文章にしても僕たちが思いつかないものをパパっと出してくれる。対外的な書類も含めて、書面に落としてくれるのは心強いです。文章作成マシーン。でも、時々めんどくさくなって、任せようとしてくるんですけどね。
山崎さん:あらゆる作業がシステム化されたことで、運営がかなり楽になりました。見える化されて運営フローが変わったりした分、忙しくなった部分もあるんですけど。
大学祭や課外活動は、新しい視点を見つけるきっかけになる。
— そもそも、大谷さんにとって大学祭ってどんな存在なのでしょうか。ただのお祭り好きというよりは、何か特別な思い入れを感じるのですが。
そうですね。もちろん楽しむ、遊ぶというのも大学祭の魅力のひとつだと思いますが、僕にとって大学祭は、研究にも活きる多様な視点を見つけられる場です。「大学は勉強する場だから、課外活動はいらない。大学生は勉強だけしていなさい」という意見、耳にしたことありませんか?僕は、この意見が大嫌いなんですけどね(笑)。これは決して、研究一筋の方を否定しているのではありません。もちろんそういう人も必要で、研究一筋だからこそ見えてくるものもあると思うんです。僕が人文系の研究をしていて思うのは、視点っていろんなところに落ちているということ。例えば、ニュートンはりんごが落ちるのを見て重力を発見したわけじゃないですか。これと同じで、課外活動はただ遊んだりハメをはずしたりというのではなく、研究のうえで大切な視点を見つけるためにやっているような気がしています。

それに、文化系の団体の中には、大学祭をひとつの目標に活動しているところもあると思います。そうした団体の取組や成果をお披露目する場としても、社会に開けた多様性のある場を築くうえでも、大学祭は必要不可欠だというのが僕の考えです。
開催はどうなる?中実の動きと、まちかね祭のこれから。
— 延期が決定してから、今はどんな動きがあるんでしょうか?開催は実現しそうですか?
開催する、しないについては、今は何ともお答えできない状況です。学生団体の皆さんへアンケートをとり、その集計結果やコロナの状況を見ながら、慎重に判断したいと考えています。ただ、いつまでも延期状態にしておくのではなく、まちかね祭を開催するなら3月までに実現したいです。
— なぜ3月?
1年生にとっては初めてで、4年生にとっては最後の大学祭ですから。
— 開催に向けて、8ヵ月もの時間をかけて準備を重ねてこられたと思います。それが延期になってしまった今、どういうお気持ちですか?
開催を楽しみにしていたのですが、感染者数が急激に増えているのを見て、本当に開催して良いのか委員長として判断しづらい状況でした。大学当局から「中止」ではなく「延期」の勧告があったことに、内心ほっとしています。それに、「延期」で良いんだと安心しました。
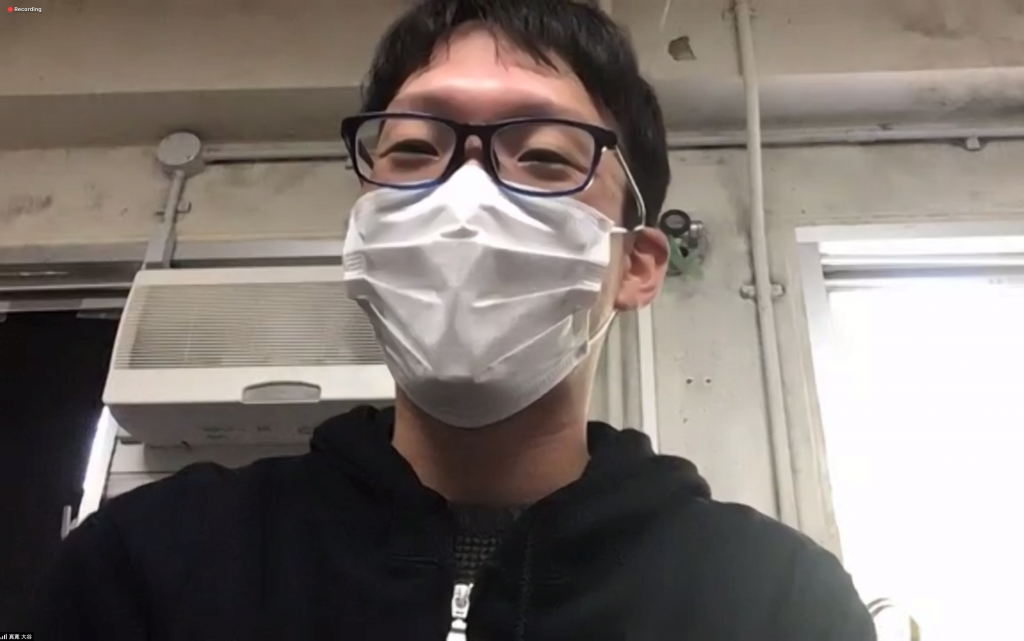
— この記事を読んでくださっている方に、メッセージをお願いしいます。
確実に開催するとは断言できませんが、何かしらの形でまちかね祭を実現したい。そのために、今できる最大限のことを中実では行っています。期待はしないでもらいたいのですが、今後の動きを楽しみに待っていてください!
番外編:
まちかね祭が予定通り開催されていたら。本当は声を大にして、大谷さんが皆さんに伝えたかったメッセージ。
まずは学生団体の皆さんへ。イベント来場者の皆さんの安全確保という理由から、団体の皆さんにはやってはいけないことを厳しくお伝えし、中実は団体の敵のような風土がここ何年かで培われてしまっていたことに、我々は深く反省を重ねてまいりました。そのことを、まずは知っておいてもらいたいです。そのうえで今年は、感染症対策を徹底しながら、コロナ禍でもできることをできる限り実現できるように、皆さんファーストで準備してきたつもりです。大学祭の実施にあたって守るべきことは守りながらも、楽しんでいただければと思います。
そして、イベントに参加されるお客様へ。今年のまちかね祭のテーマは、「日常にもう一度彩りを。」です。我々学生と大学が一丸となり、約8ヵ月かけて少しずつ形にしてきました。感染症対策を守っていただきながら、大阪大学の大学祭を、阪大生のおもしろさを味わってもらえたら嬉しいです。そして日本でほぼ唯一開催される大学祭を皆さんと一緒につくりあげ、賑わいを全国に届けられたらと思っております。ではまちかね祭でお会いしましょう!


