
橋爪 節也 先生
大阪大学社学共創本部教授
総合学術博物館/大学院文学研究科/適塾記念センター(兼任)。
総合学術博物前館長

道頓堀の雨に別れて以来なり―川柳作家・岸本水府とその時代 上巻
田辺聖子 著
ISBN:9784122037090 | 出版社:中央公論新社 | 本体価格:1,048円
グリコの有名なコピー「一粒300メートル」を作り、「大阪松竹歌劇団」のテーマ曲「桜咲く国」を作詞した岸本水府と、番傘川柳社を中心とする作家たちをとりあげる。読売文学賞、泉鏡花文学賞を受賞した。
江戸時代の文人研究の入門編としては、中村真一郎の『頼山陽とその時代』(1971年)、同『木村蒹葭堂のサロン』(2000年)がおすすめだが、近代大阪の文化の爛熟を知るには、本書は屈指の名著である。
舞台は大阪。タイトルの「道頓堀の雨に別れて以来なり」も水府の句。この句の「道頓堀」を「どうとんぼり」と読むか、ミナミらしく「とんぼり」と読むかは自由だが、五七五にあわせば後者となる。
水府の句碑は道頓堀の「今井」の前に「頬冠りのなかに日本一の顔」があるほか、起草に私も携わった戎橋の銘板にも「戎橋、白粉紙を散らす恋」が刻まれている。
また本書には、上方落語でもおなじみの「上かん屋へいへいへいとさからはず」の西田当百、家族とともに原爆で死んだ小田夢路はじめ、たくさんの川柳作家が登場する。
大阪の生んだ文芸への著者の愛惜の念が、しみじみ伝わるとともに、川柳を軸に戦前戦後の大阪の文化的爛熟を伝えた力作である。表紙も田辺聖子さんらしく、可愛らしく、ほつこりする。
江戸時代の文人研究の入門編としては、中村真一郎の『頼山陽とその時代』(1971年)、同『木村蒹葭堂のサロン』(2000年)がおすすめだが、近代大阪の文化の爛熟を知るには、本書は屈指の名著である。
舞台は大阪。タイトルの「道頓堀の雨に別れて以来なり」も水府の句。この句の「道頓堀」を「どうとんぼり」と読むか、ミナミらしく「とんぼり」と読むかは自由だが、五七五にあわせば後者となる。
水府の句碑は道頓堀の「今井」の前に「頬冠りのなかに日本一の顔」があるほか、起草に私も携わった戎橋の銘板にも「戎橋、白粉紙を散らす恋」が刻まれている。
また本書には、上方落語でもおなじみの「上かん屋へいへいへいとさからはず」の西田当百、家族とともに原爆で死んだ小田夢路はじめ、たくさんの川柳作家が登場する。
大阪の生んだ文芸への著者の愛惜の念が、しみじみ伝わるとともに、川柳を軸に戦前戦後の大阪の文化的爛熟を伝えた力作である。表紙も田辺聖子さんらしく、可愛らしく、ほつこりする。
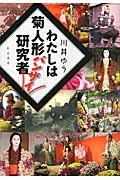
わたしは菊人形バンザイ研究者
川井ゆう 著
ISBN:9784880084336 | 出版社:新宿書房 | 本体価格:2,400円
「菊人形」といえば、ひらかたパーク。ひらかたパークといえば「菊人形」。大阪での秋の行楽の定番だったが、平成17年に96年の歴史を閉じた。
その源流には、幕末明治の大阪で盛んだった「造り物」や「生き人形」などがあり、さらに明治期の難波駅前にあった「パノラマ館」なども含め、近代的な美術が誕生する以前からある見世物は、視覚のみならず、すべて体感的で、ひとの好奇心をあおり、刺激しドキドキさせる。
著者は枚方市に生まれて「菊人形」に興味を抱いた。各地の菊人形展や菊師、人形師を訪ねるフィールドワークを重ね、ついに日本全国の菊人形を踏査するに至った。「菊人形バンザイ研究者」というタイトルに著者の照れがあるが、内容は実証的で堅実そのもの。
籠状に編まれた人形の体に、開花から、しぼむまでを計算して菊花の鉢をくみ上げるテクニックや、会期中に何度も花の種類をとりかえるなどの表現技法に迫るとともに、東京中心で語られてきた菊人形の歴史を、名古屋や岐阜の菊師らの調査も踏まえて書きかえたことは立派な業績である。
最近の流行でいえば「菊人形」は、近代日本の視覚表現のあり方や、アートとポップカルチャーの境界を考える材料であるし、祝祭における人型の民族学的研究、都市経営における「観光産業」の可能性、継承される「記憶」などを探る身近でおもしろいテーマである。
おもしろいと思うかどうかは、あなた次第。しかし気になる一冊である。
その源流には、幕末明治の大阪で盛んだった「造り物」や「生き人形」などがあり、さらに明治期の難波駅前にあった「パノラマ館」なども含め、近代的な美術が誕生する以前からある見世物は、視覚のみならず、すべて体感的で、ひとの好奇心をあおり、刺激しドキドキさせる。
著者は枚方市に生まれて「菊人形」に興味を抱いた。各地の菊人形展や菊師、人形師を訪ねるフィールドワークを重ね、ついに日本全国の菊人形を踏査するに至った。「菊人形バンザイ研究者」というタイトルに著者の照れがあるが、内容は実証的で堅実そのもの。
籠状に編まれた人形の体に、開花から、しぼむまでを計算して菊花の鉢をくみ上げるテクニックや、会期中に何度も花の種類をとりかえるなどの表現技法に迫るとともに、東京中心で語られてきた菊人形の歴史を、名古屋や岐阜の菊師らの調査も踏まえて書きかえたことは立派な業績である。
最近の流行でいえば「菊人形」は、近代日本の視覚表現のあり方や、アートとポップカルチャーの境界を考える材料であるし、祝祭における人型の民族学的研究、都市経営における「観光産業」の可能性、継承される「記憶」などを探る身近でおもしろいテーマである。
おもしろいと思うかどうかは、あなた次第。しかし気になる一冊である。

日本の祭と神賑:京都・摂河泉の祭具から読み解く祈りのかたち
森田 玲 著
ISBN:9784422230351 | 出版社:創元社 | 本体価格:2,000円
大阪の文化を知るための名著。フィールドワークをもとに祭礼の多彩な諸相を網羅しており、この分野の基本文献となる労作である。
出版社の解説には「多彩に展開する現代日本の祭を、まず神事と神賑行事に分類し、カミとヒトが織りなす基本構造から図解。神輿・提灯・太鼓台・地車・唐獅子などの祭具が、神事と密接に関係しながらも、人々の楽しみに応えて発達してきた歴史を明らかにする」とあるが、私の場合、文楽「夏祭浪花鑑」ゆかりの高津宮の夏祭りの地車を毎年きいて育った。天神祭でもコンコンヂキヂンと炸裂するお囃子である。鐘、太鼓、笛の織りなすアンサンブルや龍おどり、船を連想させる地車の形などについて知りたかったが、適切にそれが分かる本はなかった。
しかし本書の刊行で、はじめて知りたいことが分かった。鐘を叩くときの符丁のあることもはじめて知った。説明も懇切丁寧で、図や写真も多く、読者にそれを伝えようとする熱意がある。
著者の森田玲さんは、大阪府立岸和田高校から京都大学で学んだ。篠笛の演奏や指導、調査研究を行い、平成24年には第24回文化庁芸術祭大衆芸能部門・新人賞を受賞するなど、演奏家としても活躍している。
祭礼をテーマに大阪文化を伝える、こうした真摯で誠実な刊行物を見ると心が和んでくる。
出版社の解説には「多彩に展開する現代日本の祭を、まず神事と神賑行事に分類し、カミとヒトが織りなす基本構造から図解。神輿・提灯・太鼓台・地車・唐獅子などの祭具が、神事と密接に関係しながらも、人々の楽しみに応えて発達してきた歴史を明らかにする」とあるが、私の場合、文楽「夏祭浪花鑑」ゆかりの高津宮の夏祭りの地車を毎年きいて育った。天神祭でもコンコンヂキヂンと炸裂するお囃子である。鐘、太鼓、笛の織りなすアンサンブルや龍おどり、船を連想させる地車の形などについて知りたかったが、適切にそれが分かる本はなかった。
しかし本書の刊行で、はじめて知りたいことが分かった。鐘を叩くときの符丁のあることもはじめて知った。説明も懇切丁寧で、図や写真も多く、読者にそれを伝えようとする熱意がある。
著者の森田玲さんは、大阪府立岸和田高校から京都大学で学んだ。篠笛の演奏や指導、調査研究を行い、平成24年には第24回文化庁芸術祭大衆芸能部門・新人賞を受賞するなど、演奏家としても活躍している。
祭礼をテーマに大阪文化を伝える、こうした真摯で誠実な刊行物を見ると心が和んでくる。
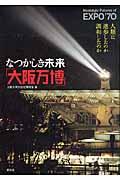
なつかしき未来「大阪万博」
大阪大学21世紀懐徳堂 著
ISBN:9784422230313 | 出版社:創元社(大阪) | 本体価格:2,300円
2025年の大阪万博には、様々な現実的問題や課題が山積されており、単純に喜んではいられない。例えば1970年に大阪千里山丘陵で開催された「日本万国博覧会」は、どれだけ検証されてきたのだろう。EXPO'70ー大阪万博を、高度成長期の経済発展の成功例ととらえ、今回の万博誘致を喜ぶならば、喜半世紀で激変した世界情勢や時代感覚が欠如していると言われても仕方がない。
2010年、大阪万博40年目の年に、21世紀懐徳堂の企画で大阪大学では万博に関するシンポジウムを開催した。大阪大学は隣接する吹田キャンパスの一部を貸与するなど、万博と無関係だったわけではなく、そのことも踏まえたシンポジウムの記録である。
特別付録として、テーマ館のサブ・プロデューサーをつとめた作家・小松左京、お祭り広場を計画した後の大阪大学工学部教授・上田篤、パブリックアートに携わった具体美術協会の今井祝雄へのインタビューがDVDが付けられ、小松のインタビューは、作家最後の音声記録となった。
EXPO'70では、平野暁臣『万博の歴史~ 大阪万博はなぜ最強たり得たのか~ 』(2017年、小学館クリエイティブ)も必読書であり、浦沢直樹の『本格科学冒険漫画 20世紀少年』も、万博から平成に至る時代精神をみごとに昇華した作品としてお勧めする。
2010年、大阪万博40年目の年に、21世紀懐徳堂の企画で大阪大学では万博に関するシンポジウムを開催した。大阪大学は隣接する吹田キャンパスの一部を貸与するなど、万博と無関係だったわけではなく、そのことも踏まえたシンポジウムの記録である。
特別付録として、テーマ館のサブ・プロデューサーをつとめた作家・小松左京、お祭り広場を計画した後の大阪大学工学部教授・上田篤、パブリックアートに携わった具体美術協会の今井祝雄へのインタビューがDVDが付けられ、小松のインタビューは、作家最後の音声記録となった。
EXPO'70では、平野暁臣『万博の歴史~ 大阪万博はなぜ最強たり得たのか~ 』(2017年、小学館クリエイティブ)も必読書であり、浦沢直樹の『本格科学冒険漫画 20世紀少年』も、万博から平成に至る時代精神をみごとに昇華した作品としてお勧めする。

GANTZ/OSAKA (愛蔵版コミックス)1
奥浩哉 著
ISBN:9784087823431 | 出版社:集英社 | 本体価格:1,619円
原著は,大阪の街が、実像とは別にどのような歪曲されたイメージで語られてきたかについて、私は『大大阪イメージ-増殖するマンモス/モダン都市の幻像』(2007年、創元社)
で述べ、最近では井上章一『大阪的-「おもろいおばはん」は、こうしてつくられた』(幻冬舎)が問題提起している。
目眩を起こしそうになるほど多様な大阪イメージのなかで、独自の視点でそれを視覚化したのが奥浩哉のマンガ『GANTZ』の「ぬらりひょん編」である。
ぬらりひょんを総大将とする妖怪軍団と、ガンツのメンバーが壮絶な死闘を演じる舞台が道頓堀であり、リドリー・スコット監督の映画『ブラック・レイン』(1989年)に登場した高松伸設計のKPOキリンプラザ大阪も健在で、大阪チーム最強の「岡八郎」の風貌も『ブラック・レイン』が遺作となった松田優作そっくりである。
一方、吉本新喜劇のテーマで登場する妖怪たちは、大徳寺真珠庵本・伝土佐光信筆「百鬼夜行絵巻」や、鳥山石燕『画図百鬼夜行』、水木しげるの作品などから採用され、和風でクラシック。どこか憎めない妖怪たちが一斉に凶暴化し、この奇妙なアンバランスが、世紀末的な雰囲気を醸し出す。
川柳の岸本水府が愛した古き良き伝統ある道頓堀の街が無残に破壊されていくのだが、「いまや大阪名物!・巨大妖怪!」とキャッチコピーが画面にあっても納得する迫力であり、大阪文化研究の資料として、ここはブックオフの100円コーナーではなく、判型の大きい愛蔵版を手に入れるほかない。
目眩を起こしそうになるほど多様な大阪イメージのなかで、独自の視点でそれを視覚化したのが奥浩哉のマンガ『GANTZ』の「ぬらりひょん編」である。
ぬらりひょんを総大将とする妖怪軍団と、ガンツのメンバーが壮絶な死闘を演じる舞台が道頓堀であり、リドリー・スコット監督の映画『ブラック・レイン』(1989年)に登場した高松伸設計のKPOキリンプラザ大阪も健在で、大阪チーム最強の「岡八郎」の風貌も『ブラック・レイン』が遺作となった松田優作そっくりである。
一方、吉本新喜劇のテーマで登場する妖怪たちは、大徳寺真珠庵本・伝土佐光信筆「百鬼夜行絵巻」や、鳥山石燕『画図百鬼夜行』、水木しげるの作品などから採用され、和風でクラシック。どこか憎めない妖怪たちが一斉に凶暴化し、この奇妙なアンバランスが、世紀末的な雰囲気を醸し出す。
川柳の岸本水府が愛した古き良き伝統ある道頓堀の街が無残に破壊されていくのだが、「いまや大阪名物!・巨大妖怪!」とキャッチコピーが画面にあっても納得する迫力であり、大阪文化研究の資料として、ここはブックオフの100円コーナーではなく、判型の大きい愛蔵版を手に入れるほかない。
橋爪 節也 先生
大阪大学社学共創本部教授
総合学術博物館/大学院文学研究科/適塾記念センター(兼任)。
総合学術博物前館長
(2019年1月対決分)
本があるのは…
- 生協 豊中書籍ショップ
- 生協 医学部書籍ショップ
- 生協 本部前店・工学部書籍ショップ(センテラス2F)
- 生協 箕面キャンパスショップ シャンティ
- 附属図書館・総合図書館(豊中)・理工学図書館(吹田)
前の書評がよめるのは…
- 生協書籍ショップと図書館にある冊子
- 生協HP内のブックコレクションページ ⇒
- Facebookページ ⇒(Facebookで「ブックコレクション」と検索)
あなたも書評を書いてみませんか?
来年度の参加団体も募集中です。 部活、サークル、研究室など、 「ぜひ書評を書いてみたい!おすすめしたい本がある!」という方は、ブックコレクションまでご一報ください♪

