
「ひと」とは何か? 古来から人々が問うてきた大きなテーマ。 生命は未だ神秘のベールに包まれ、今なおあらゆる角度から挑み続ける研究者たち。
2022年のいま、「ひと」はどこまで明らかになったのか? アンドロイド研究の第一人者石黒浩教授(基礎工学研究科)らが語る 人の正体に迫る挑戦の物語。
そう遠くない未来、私たちの家庭にもロボットが入ってくるだろう。あるときは掃除、洗濯、食器洗いを文句ひとつ言わずにこなしてくれる。あるときは優秀な秘書のようにスケジュールを管理し、仕事に必要な資料はインターネットから瞬時に集めてくれるかもしれない。頼もしいアシスタントのおかげで生活は飛躍的に便利に、そして豊かになる。でも、それだけで私たちは本当に満足できるだろうか。どこか物足りなさを感じはしないだろうか? 物足りなさを埋めてくれるロボットがあるとすれば、一つの理想は「ドラえもん」だと大阪大学大学院基礎工学研究科の長井隆行教授(システム創成専攻)はいう。言い換えれば「友達みたいなロボット」。どんな風にすればドラえもんを造ることができるのか。研究を突き詰めていくと、「人間の知能の本質は何か」という謎が浮かび上がってくる。

私たちをつくっているのは、全身で“感じる”経験値
「僕自身、人付き合いが苦手だし、友達も少ない。家族はいても、ずっと一緒にいられるかどうかは分かりません。自分が一人きりになったときを想像すると、そこはかとない寂しさを感じます。そんなとき本気で付き合えるような、人間同士の関係性みたいなものが築けるロボットがいてくれればいいなと思う」
いまは愛玩用のペットロボットがたくさん売り出され、ストレスに満ちた時代を生きる人々をいやしてくれる。高性能のコンピューターを内蔵したペットロボットは一人一人の人間を識別し、相手によってふるまいを変える。こうしたロボットに<心>を感じる飼い主も多いだろう。
だがペットロボットとドラえもんには決定的な違いがある。それは人間と同じような<知能>を持っているかどうかだ。そそっかしくて感情的なドラえもんに「知的」という形容詞はそぐわない気もするけれど、長井教授は「何か辛いことがあったとき、人間同士なら相手の辛さを自分のことのように感じ、共感することができる。つまり相手の気持ちを自分に置き換えて理解できる。それが人間の知能の本質なんです。しかし今のロボットには絶対にできない」という。
そして、こうした知能を育てるキーワードが「身体性」なのだ。
音声認識や画像認識の研究に取り組んでいたころのこと。人がしゃべっている言葉を人工知能(AI)に理解させようとして越えられない壁があった。アナウンサーがきれいにしゃべる言葉は99%の精度で認識できても、友達同士がしゃべっているような会話だと5割とか6割にダウンしてしまう。文法的に正しく話していないからなのか、活舌が悪いせいなのか。しかし、それでも人間が理解できているのはなぜだろうか。
手がかりがつかめないでいるとき、転機となる体験があった。
「駅のホームに立っていると、線路の上で何かがキラッと光りました。ペットボトルが転がっているのだとすぐに分かりました。AIでも、光のパターンからそれをペットボトルだと認識することはできますが、人間のようにはいきません。私が分かったのはなぜかと考えたとき、もともとペットボトルには飲み物がはいっていて、誰かがそれを投げ捨てた――という光のパターンの裏側にあるストーリー、それを瞬時に予測したからだと気付いたんです。ペットボトルを開けるとか、中に入っている液体を飲むとか、空になって邪魔な容器をゴミ箱に捨てるとか、それまでに自分が身体を使って積み重ねた経験がそれを可能にしたんです」
この体験を契機に、人間と同じような<知能>を育てるには「身体を備えたコンピューター」、つまりロボットの研究が必要だと考えるようになった。
ロボットには、ロボットの気持ちがある
ロボットが人間と仲良く暮らすには何が必要か。長井教授は「感情を持たせること」だと考えている。そのためは脳に相当するAIと、モーターや電池などから成る身体(メカ)との連係が重要になってくる。
「人間の子どもでも、喜怒哀楽のような感情を最初から持っているわけではありません。おいしいものを食べているときの幸せ感など、似たような身体的体験を集めて分類し、<ハッピー!>みたいな概念を頭の中で形成していくのです。同じようなことはロボットの身体情報をAIが収集、整理することで可能になります。もちろん人間の満腹感と、ロボットのバッテリーが充電された感覚はたぶん違う。しかし類似した感覚を言葉と結び付けて、『僕、今うれしいよ』と言うようにはできる。それが人間と同じ感情かといわれればちょっと違うでしょうが、ロボットなりの『うれしい』ではある。人間の喜怒哀楽も全員が同じではありませんが、それでもコミュニケーションは成り立っています」
だが感情を持たせても、人間の友達となるにはさらなる壁がある。自分と他者との関係を理解する、心理学で<自他分離>と呼ばれる高度な認識を持てるかどうかである。

わたしとあなた
「赤ちゃんが自然に言葉を覚えるのと同じやり方でロボットに言葉を覚えさせる研究をしました。1、2歳児程度の単語を覚え、簡単な言葉を発することはできましたが、3、4歳児の言語能力は持てません。なぜかというと、今のロボットでは自分と他者という概念を持てないのです。僕のことを『長井』と呼ぶことはロボットにもできます。でもそれはペットボトルを指さしてペットボトルと呼ぶのと同じ。自分と同じ仕組みで動いている他者という存在が理解できない」
これでは社会性を持つことはできないが、実は生まれたばかりの赤ちゃんも自他分離ができないという。
「赤ちゃんはお母さんやお父さんも自分の一部と思っています。それが2歳、3歳と成長するにつれ、自分と他者が分離され、『この人も自分と同じように気持ちを持っている』と分かってきます。そしてここが重要なポイントなんですが、自分とお母さんの区別がつくようになっても、一緒だったときの情報は赤ちゃんに残るんです。だからお母さんが何かを食べて<おいしそう>だというのを、自分の経験として感じることができる。涙を流しているお母さんを見てロボットは『お母さんが泣いている』とは言えますが、泣くということがどういうことかは理解できない。赤ちゃんはお母さんが泣いていると、自分まで悲しくなってしまう」。

共に学び、遊び、育つ
相手の痛みや悲しみといった内的な心理状態を予測し、自分のことのように感じる。こうした能力はコミュニケーションの基礎となるが、その出発点である自他分離について長井教授は「非常にプリミティブなものであれば、AI技術を使ってロボットでも可能になる」と予測する。だが豊かな社会生活を営めるほどに賢くなるには、人間の子どもたちに混じって多様な体験を重ねることが必要だ。
「保育園や幼稚園で子どもたちを観察していると、小さい子は最初バラバラに遊んでいるんですが、だんだん友達を作ってまとまります。それはお互いが真似をしあって一体感を高めていくプロセスです。しかし4歳くらいを境にまたばらけてくる。でも、それはたんに1歳児に戻るのではなく、ある種の協調の中でのばらけなんです。園児はそれぞれ得意なことは違うし、経験も違う。そうした多様性が効いてきて、うまく役割分担するようになる。しかし、必要があればまた一緒になっていく。それを繰り返していくのです」
子どもたちは友達との相互学習を通じて、協調性や社会性を身に着けていく。ロボットにもこうした学びのプロセスが必要となる。長井教授は今後数年ぐらいで、ロボットを実際に幼稚園に通わせ、子どもたちと一緒に遊ばせたり、席を並べて学ばせる研究プランを抱いている。
社会性を持ったロボットはやがて喜怒哀楽のように単純な感情だけでなく、嫉妬や羞恥心などという社会的感情をも持つかもしれない。ドラえもんのように人間の子どもたちと友情を育むことも絵空事とはいえない。そうなれば人間とロボットを区別する意味はどこにあるのか?
未来への架け橋
「未来はロボットと人間が対等な関係で共存している社会であってほしい。幼稚園や小学校の生徒の半分くらいがロボットで、友達として人間と一緒に遊んでいるような社会になればよい。ロボットを造った人間には彼らの面倒をみてあげる責任があるし、ロボットも人間のことを考えてくれ、お互いが得手不得手を補い合って生きていくべきです」
一方で別のシナリオもあり得る。人間の社会でも差別や争いが絶えない。ロボットとの間で摩擦が起きることも十分考えられる。AIやロボットの能力が人間を凌駕し、人間が職を奪われるという予想も現実味を帯びる。ロボットにどこまで高度な知能を与えるべきか、倫理的な問題も浮上するだろう。
長井教授は「科学者や技術者は様々な可能性を社会に示し、議論を進める責任がある」という。一方で「今の価値観で決めてはいけない。未来の世代が決めること」とも語る。ロボットとともに人間も賢くなることが求められている。
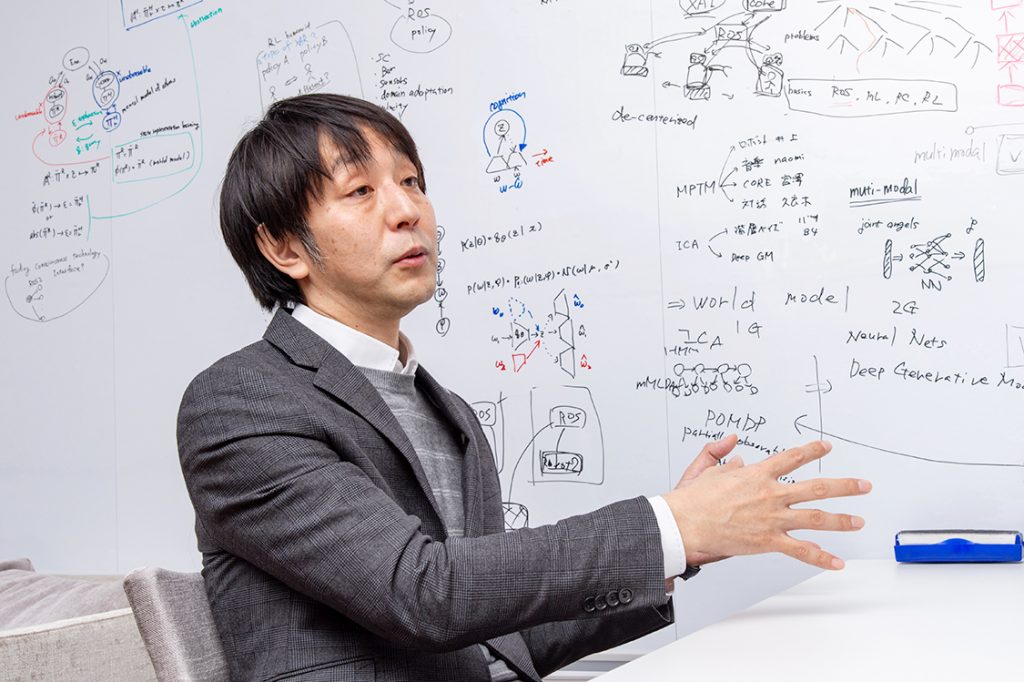
- 長井教授にとって研究とは
- 自分の好きなことができる楽しい活動、趣味の一環みたいなものです。妄想というか仮説というか、自分の考えたことをコンピューターで検証し、それなりに正解だったと思えたときはうれしい。若いころ、音楽活動に熱中していましたが、なかなか曲ができないときの苦しみとか、できたときの喜びとかが研究とまったく同じなんです。もしかすると創造性みたいなものと関係しているのかもしれません。
長井 隆行(ながい たかゆき)
大阪大学大学院基礎工学研究科 教授
2021年3月取材

「ひと」とは何か? 古来から人々が問うてきた大きなテーマ。 生命は未だ神秘のベールに包まれ、今なおあらゆる角度から挑み続ける研究者たち。
2022年のいま、「ひと」はどこまで明らかになったのか? アンドロイド研究の第一人者石黒浩教授(基礎工学研究科)らが語る 人の正体に迫る挑戦の物語。
<<<マイハンダイアプリにて順次公開予定!>>>
アンドロイドに「わたし」をみる 技術がひとを多様にし、不幸をひとつひとつ消し去っていく 基礎工学研究科 石黒浩栄誉教授
あなたはなぜ“やわらかい”のか。 知能と身体の深い関係 基礎工学研究科 細田耕教授
幼なじみがロボットになる日 心分かち合う“相棒”となるために 基礎工学研究科 長井隆行教授
脳がつくりだす“あなたの世界” 「時間」と「ここ」と「わたし」の真実 生命機能研究科 北澤茂教授
私の心はどこに存在するのか 瞬きから覗き見る脳内の風景 生命機能研究科 中野珠実准教授
アバターの責任誰が負う?法律で描く社会のかたち 社会技術共創研究センター 赤坂亮太准教授
ロボットと歩み 人間を解く 先導的学際研究機構 浅田稔特任教授
人間は偶然を楽しむ 人間科学研究科 檜垣立哉教授


